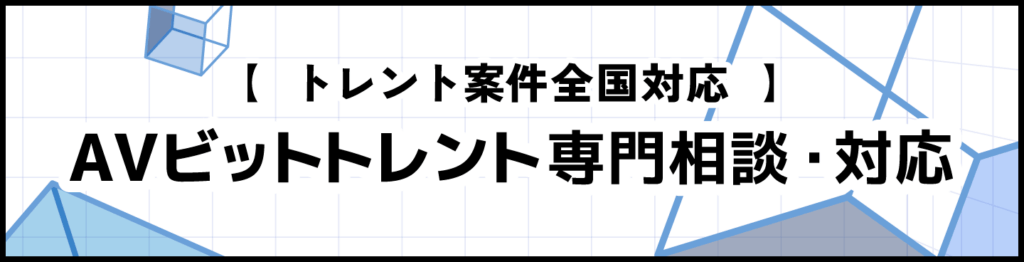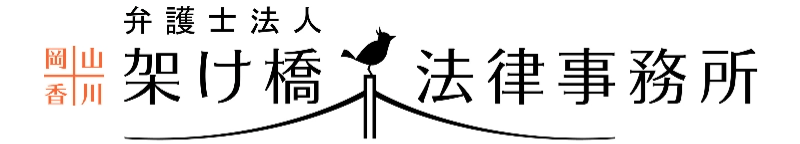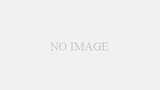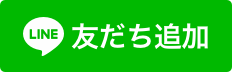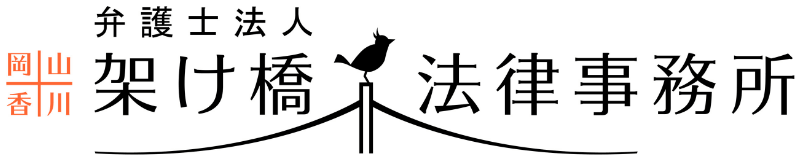この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)
出身:東京 出身大学:早稲田大学
2008年に弁護士登録後、消費者案件(出会い系サイト、占いサイト、ロマンス詐欺その他)、負債処理(過払い、債務整理、破産、民事再生)、男女問題(離婚、不倫その他)、遺言・遺産争い、交通事故(被害者、加害者)、刑事事件、インターネットトラブル(誹謗中傷、トレント、その他)、子どもの権利(いじめ問題、学校トラブル)、企業案件(顧問契約など)に注力してきた。
他にも、障害者の権利を巡る弁護団事件、住民訴訟など弁護団事件も多数担当している。
このコラムについて
トレント案件はここ数年でご相談が激増しており、多くの方がプロバイダーからの「意見照会書」に強い不安を抱いています。
中には、「自分が利用したことは事実だから」「家族や会社にばれえるのは避けたい」との考えから過度に委縮し、もはや示談に応じるしかないのではないかと囚われる方も少なくありません。
しかし、慌てる必要はありません。
ケースによっては意見照会書を不同意で回答することで損害賠償請求や刑事責任を逃れられることもあります。
そのため、意見照会を拒否(不同意で回答)する場合には、その後の法的手続きの進展を理解した上で、適切な理由を記載することが重要です。
当事務所では、年間数百件、累積1000件以上のトレント案件の相談実績に基づき、最新の動向を踏まえた最善の解決策をご提示しています。
そこで、このコラム記事では、意見照会書を不同意で回答する場合の理由や、メリットデメリット、その後の流れなどについて詳しく紹介したいと思います。
以下、順番にみていきましょう。
1トレントの利用で開示請求が届く理由は?
(1)トレントの仕組みと何が違法行為に該当するのかについて
トレント(BitTorrent)とは、P2P(ピアツーピア)通信方式によるファイル共有システムの一つです。
このシステムは、特定のファイルを小さなデータ(ピース)に細分化し、ネットワーク上のユーザー(ピア)間で分散して共有する仕組みです。
トレントの最大の特徴は、インターネットユーザーがファイルをダウンロードする際、同時に自分が既に持っているファイルの一部(ピース)を他のユーザーに提供する(アップロードする)仕組みになっている点です。
したがって、アダルトビデオ(AV)などの著作物(著作権者の許諾がないもの)をトレントでダウンロードすると、自動的にアップロード行為にも関与することになります。
これは、著作権法上の複製権侵害や公衆送信権侵害に該当する違法行為です。
なお、確認ですが、違法となるのはあくまでトレントを用いての違法アップロードや違法ダウンロードであり、ファイル共有ソフトというトレントシステムの仕組み自体が違法というわけではありません。
(2)違法アップロードの調査について
AV制作会社などの著作権者は、P2Pファインダーなど(ITJ法律事務所の場合には株式会社HDRによるBittorrent監視システム、赤れんが法律事務所の場合には株式会社utsuwa社によるシステム)のトレント監視システムを使用し、自社の著作物が違法にアップロードされた際のIPアドレスとタイムスタンプを検知します。
この情報に基づき、プロバイダー責任制限法(情報流通プラットフォーム法)に基づき、個人の契約者情報(氏名、住所など)の開示を求めてくるのです。(=意見照会書)
そして、上記のとおり、ビットトレントシステムは、ダウンロードと同時にアップロードが行われる仕組みであること、法的には民事上の責任は過失でも生じるため、「知らなかった」「気づかなかった」という弁解は通常通用しません。
また、トレント監視システムについてはその監視能力ないし証拠の正確性に疑問を呈することもあろうかと思いますが、裁判例では以下のような考え方が取られています。
IPアドレス等の特定方法の信頼性について、東京地判平成26年7月31日、東京地判平成23年11月29日及び東京地判平成23年3月14日では、権利侵害情報のダウンロード時に発信元のIPアドレス、ポート番号、ファイルハッシュ値、ファイルサイズ、ダウンロード完了時刻等を自動的にデータベースに記録する機能を有するシステムを請求者が用いる場合には、確認試験により複数回IPアドレス等の特定の結果を確認するなど、正確性が確認されること、その他当該システムによる特定方法の信頼性に疑いを差し挟むような事実がないこと等をもって、当該システムによるIPアドレス等の特定の結果に信頼性が認められるとしている。
「プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン」p8
2開示請求の二つの方法とその違いについて
(1)はじめに
著作権者(制作会社側)が開示請求を行う方法には、大きく分けて二つのルートがあります。
すなわち、裁判所の発信者情報開示命令申立手続きを用いた方法と、これを用いない任意開示請求の方法です。
これらは、それぞれの効果ないし結論、対処法が異なるのでまずはいずれのルートでの開示請求かを確認することが大切です。
(2)発信者情報開示命令申立手続きによる場合
これは、裁判所の決定に基づき発信者情報の開示を求める手続きです。
法律上は情報流通プラットフォーム法(旧称:プロバイダー責任制限法)に根拠があり、開示請求者が①権利侵害の明白性と②開示を受ける正当な理由を証明することにより裁判所が開示を命じることとなっています。
この発信者情報開示命令申立手続きは、プロバイダーから契約者に意見照会書が届くよりも前に、すでに申し立てがされているのが通常です。
この裁判所の開示命令申立手続きがされているケースでは、意見照会書に不同意で回答をしたとしても、後に裁判所からの開示命令が発令されるケースが大半です。
中には、①権利侵害の明白性が否定されて棄却になるケースもありますが、全体からすると稀です。
そして、棄却になるケースとしては
開示請求者の権利(著作権)が証明できなかった
検出されたIPアドレスが違っていた
などが典型かと思います。
いずれにしても開示命令が認容された場合には、その結果として、契約者情報(氏名、住所、メールアドレスなど)は開示請求者側に開示され、その後の示談交渉に進むことになります。
(3)任意開示請求の方法(テレサ書式)による場合
これは、裁判所を介さずに、プロバイダーが任意で情報開示に応じるよう求める方法です。
以前はこの一般社団法人テレコムサービス協会の書式(テレサ書式)に基づく任意開示が多く行われていました。
その理由は、
任意開示でも同意に応じる契約者が少なくない、もしくは一定割合で存在すること
任意開示の方法は簡単で手続きも早いこと
開示請求者としても、任意での開示がされれば良いけど無理なら仕方ない、もしくは無理なら発信者情報開示命令申立手続きに移る
という点にあります。
そして、このテレサ書式による任意開示請求の場合、契約者が不同意で回答をした場合には、開示されることはまずありません(プロバイダーが独自の判断で一方的に開示するケースを除く)。
そのため、そのまま不同意とすることで開示結果を避けられる余地が十分あります。
もちろん、弁護士に依頼をしてもらって回答をすることも可能です。
ただし、一部のプロバイダーは不同意であっても開示をすることがあるため、注意が必要です。
他方で、任意開示請求で不開示となった後に、請求者が改めて裁判所の開示命令申立手続きを行うケースは現状見受けられないようです。
3意見照会書の回答方法について
(1)はじめに
プロバイダーから意見照会書が届いたら、記載された提出期限(通常1週間~2週間程度)までに、開示に同意するか不同意にするかを判断し、早期に回答書を提出する必要があります。
回答書を提出せず放置したり、無視したりすることは推奨されません。
回答しなければ、「開示請求に対する特段の主張を行わないもの」として扱われてしまうからです。
(2)同意での回答について
開示に「同意」で回答した場合、プロバイダーから開示請求者に対して契約名義人の氏名、住所などの情報が開示されます。
開示に同意すると、その後の示談交渉や損害賠償請求へと進みます。
弁護士に相談せず同意で回答してしまうと、その後の制作会社側からの高額な示談要求や訴訟リスクに直面する可能性があるため、注意が必要です。
(3)不同意での回答と回答理由について
開示に「不同意」で回答した場合、プロバイダーは開示請求者の権利が侵害されたことが明白であるかどうかを検討し、明白性が認められないと判断した場合には開示をしません。
しかし、著作権侵害行為は権利侵害性が客観的に立証しやすいため、プロバイダー側が不同意の回答であっても開示するケースは多々あります。
不同意で回答する際には、その理由を明記する必要があります。
不同意の理由として典型的に記載されるケース
これらの主張は、民事上・刑事上の責任の有無や損害賠償額の算定に影響を与える基礎情報となります。
なお、身に覚えのないトレント利用についての詳しい解説は以下の記事をご参照ください。

4同意で回答した後の流れについて
(1)制作会社からの通知について
同意で回答し、契約者の個人情報が開示されると、開示請求者(制作会社)の代理人弁護士から契約者宛に通知書が届きます。
しかし、当事務所で受任対応しているケースであれば、プロバイダーへの回答と同時に、制作会社側代理人弁護士にも受任通知を送付します。
その結果、制作会社からの通知書が契約者に届くことはありません。
家族にばれることを懸念する場合には、このタイミングで早めに弁護士を入れておくことのメリットといえます。
通知書には、示談の申し入れとして一定額の示談金が提示されるほか、刑事責任の指摘や、民事上の損害賠償額の計算(実損害の計算)が明記されていることがあります。
この通知書の内容に基づき、本格的に示談交渉が開始されます。
なお、トレント案件の示談金相場は以下の記事をご参照ください。
(2)IPアドレスに基づく他のアップロード行為の指摘
他にも、製作会社の代理人弁護士からは、利用者のIPアドレスからは他のファイルの利用についてもアップロードをした疑いがあるとの指摘を受けることがあります(ITJ法律事務所の場合)。
この点、IPアドレスは終生固定という仕組みでないことから、この指摘を真に受けてすでに開示されたのと同様の対応をしないといけないということにはなりません。
すなわち、製作会社としては、トレント検出システムに基づき当該IPアドレスから他にもトレントを用いたアップロード行為が推測されるので追加で開示請求をする余地があるというにとどまるので、実際に開示申立てがされない限りもしくは開示の結果にならない限りはこの指摘を前提としての示談は必ずしも必須ではありません。
実際、制作会社としても、記載のIPアドレスから検出されたすべての違法アップロードについて開示手続きをとっている訳ではありません。
5不同意で回答した後の流れについて
不同意で回答した場合のその後の流れは、請求方法によって異なります。
(1)任意開示(テレサ書式)による請求の場合
この場合にはプロバイダーが開示請求に応じなければ、契約者情報は開示されません。
また、現状、請求者がその後、裁判所の開示命令申立手続きに移行するケースは確認されていません。
多くの場合、この段階で問題が終結します。
すなわち、開示にもならず、開示請求者から通知書が届くこともなく終わるということです。
民事訴訟にも刑事事件にもなりません。
なお、不同意で回答したにもかかわらずプロバイダーが自主的な判断で開示をしてしまうケースも稀に存在するため、対応には慎重さが求められます。
(2)発信者情報開示命令申立手続きによる請求の場合
不同意で回答した場合には、プロバイダーは裁判所に対し「契約者から不同意の回答があった」旨を伝え、契約者からの不同意の理由に基づき主張立証を展開してくれます。
裁判所はプロバイダからの主張等も踏まえつつ、最終的には権利侵害の有無を判断しますが、現状、多くの場合、開示命令が発令されます。
開示命令が発令されると情報が開示され、その後の流れは「同意で回答した後の流れ」(示談交渉の開始)と同様になります。
6意見照会書の回答のために弁護士ができること
(1)専門知識による適切なアドバイス
トレント問題の解決には専門性が不可欠です。
回答書の作成、提出の局面とその後の流れに関しては、
① 届いた意見照会書が発信者情報開示命令を経ているものか、それとも任意開示請求の方法(テレサ書式)によるものかの区別や判断
② それぞれのケースに応じて回答書を同意で出す場合、不同意で出す場合のメリットデメリットの説明
③ 回答書提出後の手続きの流れや示談の見通し
④ 民事訴訟になる可能性の大小の判断
⑤ 刑事事件(逮捕など)になる可能性の大小の判断
⑥ これらを避けるための対応や示談金ないし和解金減額、示談拒否の対応
などが可能です。
また、当事務所の弁護士は、これまで1000件を超える相談実績を通じて、相手方弁護士(ITJ法律事務所、赤レンガ法律事務所、オルビス法律事務所、八重洲コモンズ法律事務所など)の最新の動向や、損害賠償額の算定に関する3つの主要な裁判例(東京地裁、知財高裁、大阪地裁)を深く理解しています。
この専門知識に基づき、ご依頼者様の個別事情(複数の開示請求の可能性や経済状況)を考慮した、最善かつ間違いのない確実な解決策を提案できます。
また、これまでに民事訴訟の対応経験も複数あることから、万が一、民事訴訟になったとしても経験に基づく安心安全な解決に導きます。
その際、依頼者のプライバシーといった権利を考慮し、家族や会社に知られずに解決できた事例もあります。
当然、刑事事件という最悪の事態を避けるための知識経験も豊富です。
この点、著作権侵害は親告罪であり、著作権者の告訴がなければ刑事処分には至りません。
しかも、示談が成立すれば、刑事罰にならず、前科もつきません。
そして、弁護士は相手方弁護士との交渉窓口となり、示談の可能性に向けて交渉を進めます。
ご安心してお任せください。
(2)精神的負担の軽減
突然の意見照会書は、強い驚きと不安を伴います。
しかも、プロバイダーのログ期間に照らし、最終的な解決まで長期に渡る不安に苛まれることとなります。
そうした中、弁護士に依頼することで、煩雑なプロバイダーへの対応や、相手方弁護士との交渉窓口を全て引き受けます。
当然、専門家によるサポートの結果、日々の安心した生活を取り戻すことに繋がります。
また、当事務所の「即示談以外の解決」という方針のもと、ログ保存期間の経過を待ち、追加の請求リスクをゼロに近づけてから最終結論を出すことで、

「一旦示談したけどまたすぐ届いた」
という再度の不安を回避・少なくし、依頼者様の精神的負担を軽減します。
【 呉弁護士の一言コメント 】

当事務所が受任をすると、制作会社側の弁護士との交渉の窓口となり、かつ相手方弁護士からは以後の請求や督促がピタッと止まることが大半です。
その意味でも弁護士に依頼することのメリットは大きいかと思います。
なお、当事務所におけるトレント案件のご相談から受任、その後の対応までの流れは以下からご参照ください。
7法律相談・弁護士費用
当事務所は、トレント案件の複雑化、プロバイダー対応の多様化、ログ保存期間経過待ちによる対応期間の長期化などを踏まえ、2025年に費用の改定を行っています。
以下、ご確認ください。
(1)法律相談
また当然ではありますが、ご相談内容が外に漏れることはなく、秘密を厳守いたします。
トレントのようにプライバシー性の高い案件であるからこそ、この点をご心配される方が多いのも事実です。
また、意見照会書の回答期限の関係から迅速な対応を心がけており、可能な限り即日のご相談もお受けしています。
トレントの件でお困りの方は、ぜひ一度当事務所にお気軽にお声がけください。
あなたにベストな対処法をご案内いたします。
(2)着手金等
費用プランは、「通常プラン」「おまとめプラン」「訴訟プラスプラン」があります。
特にログ保存期間の長短に応じた適正な料金設定を行うために「おまとめプラン」が細分化されています。
| 種別 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常プラン | 220,000円 (税込) | 示談解決:165,000円 (税込) 請求断念:220,000円 | 1.以前の165,000円から改定されました。 2.2社目以降:着手金 1社あたり77,000円(税込)| 報酬金 同額 |
| おまとめプラン | ショートコース 275,000円(税込) | すべての開示請求に対する事案処理が完了した際:275,000円 ※示談・請求断念問わず | 1.開示請求が届いた案件数、会社数を問わず、すべての案件について弁護士対応が可能です。 2.本件についての受任期間は、プロバイダーのログの保存期間を勘案し1年未満とします。 プロバイダー:笠岡放送㈱、井原放送㈱、㈱ケーブルメディアワイワイ、大分ケーブルテレコム㈱、その他ログ保存期間が1年未満のプロバイダー |
| ノーマルコース 308,000円(税込) | すべての開示請求に対する事案処理が完了した際:308,000円 ※示談・請求断念問わず | 1.開示請求が届いた案件数、会社数を問わず、すべての案件について弁護士対応が可能です。 2.本件についての受任期間は、プロバイダーのログの保存期間を勘案し2年未満とします。 プロバイダー:ショートコース、ロングコース以外のプロバイダー | |
| ロングコース 363,000円(税込) | すべての開示請求に対する事案処理が完了した際:363,000円 ※示談・請求断念問わず | 1.開示請求が届いた案件数、会社数を問わず、すべての案件について弁護士対応が可能です。 2.本件についての受任期間は、プロバイダーのログの保存期間を勘案し2年6ヶ月未満とします。 プロバイダー:ソフトバンク㈱、㈱NTTドコモ、㈱オプテージ、エネコム、㈱新潟通信サービス、その他ログ保存期間が2年以上と当事務所で判断しているプロバイダー | |
| 訴訟プラスプラン | おまとめプランの着手金+ 110,000円 (税込) | すべての開示請求に対する事案処理が完了した際:おまとめプランの報酬+110,000円 ※示談・請求断念問わず | 1.おまとめプランに、「万が一民事訴訟になった際の弁護士費用(着手金と報酬金)」を予めプラスにしたプランです。 このプランをご選択の場合、万が一、民事訴訟を提起されたケースでも左記金額にて民事訴訟の対応(一審まで)を行います。 2.複数社からの訴訟提起にも対応いたします。 |
8よくあるご質問
-
1.示談を拒否した場合、必ず訴訟になりますか?
-
示談を拒否したり、交渉がまとまらなかったりした場合、理論上は民事訴訟(損害賠償請求訴訟)を提起される可能性はあります。
しかし、当事務所の取り扱い事例では、不同意や示談拒否をしたとしても、実際に刑事事件になったケースは見受けられません。
また、過去の裁判例では、制作会社が請求した高額な損害賠償額(数千万円)に対し、裁判所が実際に認めた賠償額は数万円程度にとどまった事例があります。
これは、裁判所が損害賠償額の算定において、ダウンロード版の利益額や利用期間を限定的に認定したためです。
当事務所では訴訟対応の実績もあり、万が一の際にはご依頼者様に有利な判断を得られるよう対応いたします。
-
2.不同意で回答すれば、家族や会社にバレずに解決できますか?
-
弁護士に依頼することで、プロバイダーや相手方弁護士との煩雑なやり取りをすべて代行しますので、ご依頼者様以外の第三者(家族や会社)が関与するリスクを軽減できます。
ただし、プロバイダは、追加の意見照会書についてあくまで契約名義人に送付するなどの対応しかとってくれないところも少なくありません。
その際には注意が必要です。
また、任意開示請求(テレサ書式)に対して不同意で回答し、開示が阻止されれば、情報が制作会社側に開示されないため、その後の交渉や請求がなく、家族や会社に知られずに解決できる可能性は高まります。
-
3. 刑事告訴される可能性はありますか?
-
著作権侵害は「親告罪」であり、著作権者(制作会社)の告訴がなければ刑事処分には至りません。
示談交渉の目的の一つは、示談を成立させることで刑事告訴を回避することにあります。
私的に少し利用した程度の事案であれば、刑事事件になるリスクは極めて低いと考えられます。
そもそも実際に刑事事件になるのは、トレントを商業的に利用していたなど、相当に悪質な事案に限られるのが実情と思われます。
過度に心配する必要はありません。
その他、トレントの問題に関するよくあるご質問は以下のページに詳しく解説をしています。
ぜひご参照ください。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所