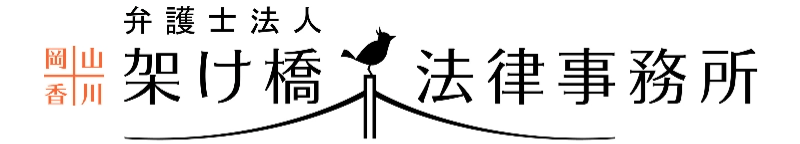1 事案の概要について
亡Bの長女である原告が、亡Bの二女である被告Y1及び亡Bの養女である被告Y2に対し、遺言公正証書による亡Bの遺言の無効確認を求めた事案において、本件遺言証書作成当時、85歳であった亡Bは、既に認知症に罹患し、その症状が進行を始めていたものと考えられ、同証書の文案及び原案の内容を十分に認識することができていなかったものと認めるのが相当であり、また、本件遺言証書の内容が、亡Bと原告及び被告Y1との関係に照らして不合理であることなどから、亡Bは遺言能力を欠いていたと判断して、請求を認容した事例
2 事案の特徴について
(1)遺言者(亡B)の遺言時の年齢
85歳
(2)遺言書の種類
公正証書(平成16年作成)
(3)遺言者の精神疾患の状況
認知症に罹患し、その症状が進行を始めていた
(4)原告
遺言者の長女
(5)被告
遺言者の次女(Y1)
次女(Y1)の次女(Y2)(遺言者と養子縁組をしている)
(6)遺言書の内容
遺産たる不動産をY1及びY2に各2分の1の割合で相続させる
(7)遺産の内容
ほぼ遺産たる不動産のみ
3 遺言無効を認めた裁判所の判断枠組みについて
(1)遺言能力の欠如を理由とした遺言無効の判断基準について
遺言能力の欠如を理由として遺言無効を判断する際、裁判所は遺言能力の定義をした上で、当該事案を当該定義にあてはめて遺言無効の判断をすることが多いです。
そして、遺言能力の定義はいまだに画一的、統一的な定義がある訳ではなく、裁判例ごとに異なる定義づけがなされています。
とはいえ、その定義内容をつぶさに分析すると、決してその場限りの定義がされているものでもなく、裁判例ごとに共通点がまったくないということでもありません。
この点、遺言能力についての考え方は以下の記事の中で詳細に説明をしているのでご参照ください。
(2)本件裁判例における遺言能力の定義づけについて
では、本件裁判例で遺言能力がどのように定義づけされているかですが、裁判例を分析する限り、遺言能力の定義をした箇所は見受けられませんでした。
ただし、最後の結論部分において、「以上の事情を総合して考慮すると」とした上で遺言無効の結論を導いていることから、本件裁判例でも諸般の事情の総合考慮により結論を導いていることは明らかであり、このことは遺言無効が争いになった裁判例における判断枠組みに沿うものです。
(3)本件裁判例において遺言無効の結論を導くに至った事情
以上のように本件裁判例では、事情の総合考慮により遺言無効の結論を導いています。そこで、遺言無効の結論を導くに至った個別の事情を整理してみると次のようになります。
(1)認知症の状況
(2)本件遺言書の作成手続きの状況
(3)本件遺言書の内容
(4)(1)認知症の状況について
遺言者は、平成14年にはキャッシュカードの暗証番号を忘れ、自ら預金の引き出しをすることができない状態にあった。その後、遅くとも平成17年には認知症の症状と見られる徘徊行動を頻繁に行う状態にあった。そのため平成18年以降はおよそ遺言を行うことなどは不可能な状態に陥っていた。
遺言書の作成された平成16年には、自ら認知能力の低下があることを自覚し、被害妄想発言をし、はいかい行動などをし、買い物をしたことを忘れて同じ物を何度も買うといった行動もあった。
これらの事情からすると、遺言書作成当時、すでに認知症に罹患し、その症状が進行を始めていたといえる。
(5)(2)本件遺言書の作成手続きの状況
本件遺言書には3カ所の誤記があること、そのうち2カ所は弁護士が作成した文案の時点でもすでにあったこと、誤記の内容は遺言内容を決めるに際して重要な内容であったこと、弁護士事務所での確認や公証人からの読み聞かせがあったにも誤記の訂正がなかったことなどからすると、通常の認知能力を有する者であれば誤りに気が付かないことはおよそ考え難い。
(6)(3)本件遺言書の内容
遺言者において、次女(Y1)のみをかわいがり、原告については疎んでいたとの事情はないこと、むしろ遺言者においては次女に対する不満を抱き、その愚痴を原告に対して述べたり頼ったりすることもあったこと、度々、財産を原告と次女において二等分するように述べたり書面に書き記したりしていたこと、そのこと自体は自分の実子である二人に均等に財産を相続させるものであり何ら不自然なところはないこと、遺産の大半を被告らのみに相続させ、原告には何ら配慮しないということは不自然であること、次女(Y1)の長女(次女には遺言者と養子縁組をしたその次女の他に長女がいた)に対してすら何らの配慮もない不自然なものであることからすると、本件遺言の内容は合理性を欠く。
4 本件裁判例についてのまとめ
本件裁判例は、公正証書遺言であるにもかかわらず無効が認められた事案です。
その判断の際には、上記のとおり、認知症の症状が進んでいたこと、遺言書作成手続きの状況に明らかな誤記があるのに何らの指摘もないこと、遺言書の内容が不合理であることが考慮されています。
この点、遺言無効が争われる事案の多くでは認知症などの精神疾患の問題が指摘されます。そして、認知症などの精神疾患については、程度が千差万別であるところ、本件では財産管理能力が著しく後退していることや、徘徊行動があったことなどの事情を踏まえて認知症の症状が進んでいると判断をしています。逆に言えば、認知症の症状があったとしても、日用品程度は自分で買い物ができたり、徘徊行動のような異常行動がなかったりといったケースであればまた異なる結論になった可能性があります。
次に、本件遺言は公正証書遺言であり、文案の作成に弁護士も関与しているにもかかわらず明らかな誤記があり、これに対する指摘がないことを重視されています。法律の専門家である弁護士と公証人が関与する公正証書遺言においては、厳重に文案が作成され、何度も確認がされます。そうした中で明らかな誤記に対して遺言者が指摘をしないということは、結局は上記の認知症の症状が相当進んでいることの証拠ともなるものです。
その上で本件裁判例では、本件遺言書の不合理性について検討をしています。遺言無効が争われるきっかけの多くは、遺言書の内容が原告となる方にとって一方的に不利で不公平だという点にあります。本件でも遺産の大半を次女(Y1)とその次女(Y2)が取得するというものであり、不自然であることは明らかです(いわば原告には0で、次女らに10を渡すようなもの)。
この点、仮に長女には3とか4を、次女には6とか7を渡すという内容だった場合には、また判断が異なっていた可能性があります。その場合には、次女に多めに渡す合理的な理由があるか、もしくは原告には3しか渡さないことが不合理とはいえないかどうかが争われることとなります。
いずれにしても、本件裁判例は、まず初めに認知症の程度を丁寧に論じた上で、遺言書作成の手続き状況を分析し、最後に遺言内容の合理性に触れています。あらゆる遺言無効確認訴訟では、まずもって認知症などの精神疾患の有無や程度が相当程度重要視されること、方式違反などの形式面も重視されることに照らすと結論に至った理由も結論も妥当な判断と考えられます。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所