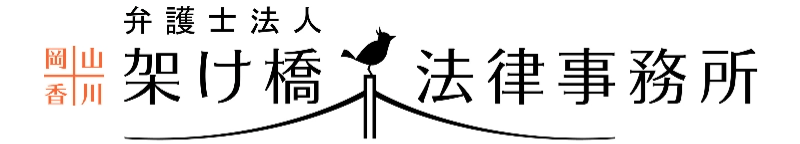1 遺言無効を主張する(したい)ケースについて
被相続人の死後、遺言書が出てきたので内容を確認したところ、相続人の一部に対して大半の遺産を相続させるとか、相続人でない第三者にすべての遺産を遺贈するとかと書かれていた場合、本来の法定相続人としては到底、納得することはできません。
特に、被相続人の身近な世話をしていた自分に対して何らの財産も遺さないという内容であればいよいよ不信感は募るばかりです。これは、生前、口頭で被相続人が遺産をどのように誰に譲り渡すつもりであると述べていた場合も同様で、口頭で述べていた内容と遺言の内容に大きな祖語があればやはり遺言の無効を考えるべきです。
他にも、相続人同士の関係が悪かったケース、被相続人が認知症でありその程度が重かったケースなども遺言無効を争うべき事案と言いやすくなります。
以下、遺言の種類として典型的な自筆証書遺言と公正証書遺言の順に遺言無効が認められるための要件を説明します。
2 自筆証書遺言とその無効について
(1)自筆証書遺言の有効要件
自筆証書遺言の無効を主張する以上は、そもそも自筆証書遺言の有効要件をしっかりと確認しておくことが必要です。
この点、自筆証書遺言の有効要件は民法968条に次のとおり定められています。
第968条
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
これを要点にまとめると以下のとおりとなります。
(1)全文の自書(ただし、財産目録の例外あり)
(2)日付の自書
(3)氏名の自書
(4)押捺
(5)訂正の際の方式の順守
(1)についてはすべての遺言内容が遺言者の自筆によらなければなりません。ただし、法改正により財産目録については印刷したものを添付することが可能となりました。その際には財産目録のすべてのページに署名捺印が必要です。
(2)については、西暦でも和暦でも構いませんが、遺言書を作成した具体的な日にちを正確に記載する必要があります。〇年〇月とだけ記載し、〇日という記載が欠けるものは認められません。
(3)については、遺言者の氏名(本名)を正確に記載してあるかが重要です。遺言書は、遺言者のその財産についての最終意思を表明するものですから誰による遺言かを明らかにするためです。
(4)の押捺は、実印による必要はありません。しかし、今どきはどこでも簡単に判子を作ることが可能ですから、管理が厳格な実印により作成されている方が慎重に遺言書を作成したと考えられやすくはなります。とはいえ、実印でなければ遺言書が無効となるものではありません。
(5)自筆で作成した遺言書を訂正するに際しては、変更箇所の特定、変更した旨の記載、署名捺印が必要です。丁寧に訂正の処理をしないとならないので、これら要件を欠くと遺言書は無効となります。
(2)自筆証書遺言が無効になる場合
ア はじめに
以上のとおり、自筆証書遺言の有効要件は厳密なものが求められています。これらを一つでも欠けばその自筆証書遺言は無効とされます。
また、(6)偽造による自筆証書遺言、(7)遺言能力なき状態で作成された自筆証書遺言も無効となることは当然です。以下、これらを理由として自筆証書遺言が無効となるケースをご説明いたします。
なお、自筆証書遺言については検認が必要とされていますが、検認を欠くことをもって遺言が無効とされるものではありませんのでご注意ください。
イ (6)偽造による自筆証書遺言について
(6)偽造による自筆証書遺言については相続人の誰かもしくは第三者が被相続人に無断で遺言書を作成する場合です。偽造の場合には全文の自筆という要件を欠くという意味ではそもそも自筆証書遺言の有効要件を満たしていないという言い方も可能です。
そして、偽造による遺言の証明としては筆跡鑑定が必須です。筆跡鑑定のためには当然、遺言者が自筆証書遺言で記載した文字と、それ以外に記した文字とを比較し、鑑定をしてもらうこととなります。鑑定資料として多数の物がある方が鑑定はやりやすくなることは明らかなので、自筆証書遺言の偽造を疑う場合には、残された自書の文書を多数探してくることが望ましいです。
ウ (7)遺言能力なき状態で作成された自筆証書遺言について
(7)遺言能力なき状態で作成された自筆証書遺言の典型は、認知症です。高齢になり認知症を患っていてその状態も軽くないもしくはむしろ重度である場合には、そもそも遺言能力が欠けることとなります。
とはいえ、遺言者が成年被後見人とされ、成年後見人が付されている場合であっても、民法上は以下の要件を満たせば遺言を有効と認めています。すなわち、成年被後見人であっても、事理弁識能力を一時回復し、医師2名以上の立ち合い等の要件があれば遺言能力を認めているのです。
第973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
また、認知症を理由として遺言能力がないとされるのは認知症がどの程度の場合かも常に問題となります。
この点、認知症の診断の際には長谷川式認知症スケール(HDS-R)やMini-Mental State Examination(MMSE)というテストが行われることが多いです。
これらテストは、テストの結果が点数で出ること、長谷川式であれば20点以下で認知症の疑い、MMSEの場合であれば23点以下で認知症の疑いとの判断目安とされていることから、これらテストの結果をもって「認知症だった以上は遺言能力がないのだ」と言いたくなるかもしれません。
しかし、認知症の最終診断やその程度については、これらテストのみで判断するものではありません。認知症は、これらテストの他にも問診や検査、これまでの病歴なども踏まえて最終的に診断されるものです。なので、これらテストの点数が低かったからといって直ちに遺言能力が否定されるものではありません。裁判例でも、これらテストの点数が低くても遺言能力を肯定した事例、これらテストの点数が高くても遺言能力を否定した事例が複数あります。
したがって、遺言能力の欠如を主張する場合には、認知症であったこと、その程度が重かったこと(軽くなかったこと)、遺言書を作成した時点でも遺言能力に疑義を投げかける言動があったこと(徘徊、物忘れ、激昂など)などを併せて主張することが重要です。
3 公正証書遺言とその無効について
(1)公正証書の有効要件
自筆証書遺言の場合と同様に、公正証書遺言においてもその有効要件を確認しておくことは重要です。
この点、公正証書遺言の有効要件は民法969条に次のとおり定められています。以下、これら有効要件を前提に公正証書遺言が無効になる場合を説明します。
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1 証人二人以上の立会いがあること。
2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は 閲覧させること。
4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
(2)公正証書遺言が無効になる場合について
ア 証人二人以上の立会いがあることについて
上記の有効要件のうち、証人の立ち合いについては、公証役場にてそもそも証人を立てないで公正証書遺言を作成するケース自体が想定し難いところです。
とはいえ、法律上は立ち合いのできる証人に要件を課しているので、その要件を満たさない証人が立ち会った場合には、そもそも証人の立ち合いがないものとして公正証書遺言の無効がいえます。
具体的には、以下の者は証人になれません。1の未成年者は遺言内容の適否や手続き順守の適否の判断をすることができないと考えられるためです。2については遺言内容に対する利害関係を持つからです。3については公証人の公証業務の公平性に反するからです。
第974条
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
イ 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することについて
遺言内容は、遺言者の財産処分に対する最終の意思表示なので、遺言者自身が述べたものでなければなりません。逆にいうと、推定相続人や第三者による誘導により作成された遺言は無効だということです。
口授というのは、遺言の内容を口頭で公証人に告げるという意味です。したがって、そもそも口を利けない場合にも口授の要件を欠きます。
ウ 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
遺言者が口授した内容を正確に筆記しているかを遺言者などにきちんと確認するための手続きであり、これが欠けるとやはり遺言は無効となります。遺言者の最終意思を公証人が確実に聞き取っているか、正確に遺言書に反映しているかの確認のための要件です。
エ 遺言者、証人、公証人による署名捺印等について
以上のようにして作成された公正証書遺言について、最後は遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名捺印をすることが必要です。実印による必要はありませんし、遺言者については署名ができなくても公証人による事由の付記により署名に代えることが可能です。
オ 遺言能力を欠く場合について
以上の公正証書遺言の有効要件とこれが欠けるために無効になる場合とは別に、自筆証書遺言の項でも説明したとおり、遺言能力が欠ける場合にはやはり公正証書遺言であっても遺言が無効となります。したがって、この点については上記の「ウ (7)遺言能力なき状態で作成された自筆証書遺言について」の項をご参照ください。
4 遺言無効の主張に関するまとめ
自分の大切な人が亡くなり、悲しみに明け暮れる中、突然遺言の存在を知り、その内容に驚き慌てて相談に来られるケースがあります。
生前の被相続人との関係、他の相続人との関係、被相続人の症状に照らすと到底、こんな内容の遺言を作成するはずはないと確信できるが、これをどうやったら覆せるのか不安に感じることでしょう。同時に、他の相続人が被相続人に取り入って遺言書を作成させたとか、そもそも当該遺言書自体が偽造なのではないかとの疑念も湧いてくるかもしれません。こうした状況において大切なことは、こんな遺言を有効とは認められないので法的に争うという気持ちと遺言無効で勝つために必要な知識や証拠の収集です。
当然、容易に勝てる争いではないので専門家である弁護士への相談や委任も必須になります。
したがって、遺言無効を疑った場合には、その後の対応に向けた周到な準備が重要です。
5 遺言無効の主張と弁護士への相談、依頼の要否やメリットについて
以上のように、遺言については自筆証書遺言であろうと公正証書遺言であろうとそれぞれに対して厳格な法律上の要件があること、これを具備していたとしても一定の場合には無効となり得ること、他方で遺言無効を勝ち取るためには診断書、カルテ、介護記録、介護認定記録などといった大量かつ専門的な文書をすみやかに過不足なく取り付ける必要があること、またこれら文書を医療などの専門的知識を前提に法律的観点から分析した上で裁判所に具体的な主張立証としてまとめる能力が必要であること、遺言無効については勝ち負けがハッキリしており中庸な解決が難しいこと、勝っても負けてもその後の遺産分割や遺留分侵害額請求などの問題が必ず付いて回ることから、他の訴訟類型と比較しても弁護士への相談や依頼が必要不可欠な事例だと言えます。
言葉を恐れずに言うならば、弁護士に依頼することなく遺言無効を争うことはリスクでしかありません。裁判所であれば分かってくれるだろう、自分で取りつけたカルテなどを出せば足りるだろうという次元の問題ではないのです。
したがって、遺言無効を考えた際にはすぐに弁護士への相談と依頼を検討なさってください。
「こんな遺言、おかしい。」という気持ちをご自身だけで抱え込まず、法的な観点からご自身の思いを形にして欲しいと思います。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所