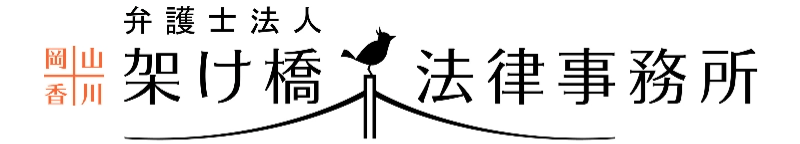1 事案の概要について
(1)原告からの請求の概要
亡Aの相続人である原告X1及び同X2が、被告に対し、以下のとおり請求をしました。
【主位的請求】
亡A作成の自筆証書遺言につき無効確認を求めるとともに、同じく相続人である被告に対し、それぞれ原告らの法定相続分に従い、本件土地についてされた所有権移転登記の更正登記手続、亡Aの遺産からの引出金及び同遺産の売却益並びに亡A名義の預金口座から被告が引き出した金員の支払を求める。
【予備的請求】
遺留分に従い上記各支払を求める。
【判決要旨】
本件遺言書作成当時、亡Aは高度に認知症が進行した状態にあり、単純な内容とはいえ、原告X2に一切財産を相続させない一方で被告に全財産を相続させるというような本件遺言書の内容を理解していたとは認められないから、亡Aに遺言能力はなかったなどと判断し、主位的請求を全部認容した。
2 事案の特徴について
(1)遺言者(亡A)の遺言時の年齢
86歳
(2)遺言書の種類
自筆証書遺言(平成18年6月18日作成)
(3)遺言者の精神疾患の状況
重度のアルツハイマー型認知症
(4)原告
亡Aと亡Bとの間の子、亡Aと亡Cとの間の第1子
(5)被告
亡Aと亡Cとの間の第2子
(6)遺言書の内容
財産をすべて被告に相続させる
(7)遺言能力
否定(遺言無効を認める)
3 遺言無効を認めた裁判所の判断枠組みについて
(1)遺言能力の欠如を理由とした遺言無効の判断基準について
遺言能力の欠如を理由として遺言無効を判断する際、裁判所は遺言能力の定義をした上で、当該事案を当該定義にあてはめて遺言無効の判断をすることが多いです。
そして、遺言能力の定義はいまだに画一的、統一的な定義がある訳ではなく、裁判例ごとに異なる定義づけがなされています。
とはいえ、その定義内容をつぶさに分析すると、決してその場限りの定義がされているものでもなく、裁判例ごとに共通点がまったくないということでもありません。
この点、遺言能力についての考え方は以下の記事で詳細に説明をしているのでご参照ください。
(2)本件裁判例における遺言能力の定義づけについて
本件裁判例では、遺言能力の定義づけについて下記のとおり論じています(分かりやすくするため番号を付しています)。その上で本件裁判例では、かかる定義にしたがって遺言能力の有無を判断しています。
記
遺言能力の有無は,(1)遺言の内容,(2)遺言者の年齢,(3)病状を含む心身の状況及び健康状態とその推移,(4)アルツハイマー型認知症(以下「認知症」という。)の発症時と遺言時との時間的関係,(5)遺言時とその前後の遺言者の言動及び精神状態,(6)遺言者の日頃の遺言についての意向,(7)遺言者と相続人との関係等遺言者の状況を総合的にみて,遺言の時点で,遺言の内容を判断する能力があったか否かによって判断されると解すべきである。
(3)(1)遺言の内容について
財産を全て被告に相続させるという単純な内容であり、その内容を理解することは客観的に容易であった。
(4)(2)遺言者の年齢
本件遺言書作成当時、86歳と高齢。
(5)(3)ないし(7)について
遅くとも平成17年5月頃には認知症を発症していた。同年11月21日の時点で自分の弟が分からない状態になることもあった。平成18年1月以降は、原告X2の名前を間違うこともあった。
本件遺言書作成時は、認知症の発症から約1年が経過した時点である。
認知機能障害の有無を捉えることを主目的とするHDS-Rの点数は、本件遺言書作成の約1年前の平成17年6月3日時点で22点、平成18年5月27日時点で16点、6月15日頃の時点で21点、9月7日頃の時点で11点、12月5日時点で4点であった。
6月15日付診断書には、「意識明瞭、会話も成立するが、日常生活、財産管理等の認知能力に著しい低下を認める。」と記載されている。
12月18日付鑑定書には、「日付、現在居住している場所などは答えられず、失見当識を認める。」「現在重度のアルツハイマー型認知症に罹患している。表面的な会話は成立するものの、時や場所、人の見当識障害を認め認知機能は著しく低下している。社会生活上状況に即した適切な判断をする能力は低下しており、自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要であると判定できる。」と記載されている。同鑑定をした鑑定人は、亡Aの認知症の進行は早い、亡Aは本件遺言書作成当時、自分の名前を間違えて記述していることから認知症が高度の進行程度になっていたと証言をしている。
亡Aは、平成16年頃や平成17年5月頃、実の妹に対し、被告のことを「あの野郎」「Iの野郎」などと話していた。平成17年11月頃から平成18年6月頃,原告X2は,2週間に1度の頻度で亡A方を訪問し,生活用品等を持って行っていた。このことからすると、本件遺言書作成当時、亡Aと被告との関係は、亡Aの全財産を被告に相続させるほど円満であったとは認めがたい。
(6)結論
以上の事情に照らすと、本件自筆証書は単純な内容とはいえ、原告X2には一切、財産を相続させず、一方、被告に全財産を相続させるというような本件遺言書の内容を理解していたとは認められない。
4 本件裁判例についてのまとめ
本件裁判例では、遺言能力の判断基準について上記のとおり、(1)から(7)の要素に基づき判断されるべきと論じた上で、これらの要素に対するあてはめをし、遺言無効の結論を導いています。
その際、遺言の内容は全財産を被告に相続させるといういわゆる極めて簡潔な内容であったものの、遺言者の年齢が高齢であったこと、重度のアルツハイマー型認知症であったこと、アルツハイマー型認知症の具体的症状として自分の弟が分からない、原告X2の名前を間違うこともあった、日付や現在居住している場所などは答えられない、本件自筆証書遺言の作成当時、自分の名前を間違えるということがあったなどとしています。
その上で鑑定によっても重度のアルツハイマー型認知症であると判断されていることを考慮しています。
さらには、亡Aや被告ないし原告との関係に照らすと、被告に全財産を譲るということの合理的な理由ないし動機がないとみています。
このように、本件裁判例は、遺言書の内容自体は非常に簡単なものであったものの、このような内容の遺言書を作成するに足りる動機付けもしくは、合理的理由がないことや、遺言者の認知症の症状に照らし、遺言無効の結論を導いています。
遺言能力の判断は、諸般の事情の総合考慮になるので、単純な遺言であれば容易に理解ができるので遺言能力があるとの結論になるとは限りません。いくら遺言の内容が容易なものでも、そのような遺言を作成する動機があったか(言い換えるとその遺言によって財産を相続することになる相続人との関係は円満であったのかどうかなど)、遺言書作成時の認知症の症状ないし程度はどうだったかなどという事情を加味して判断されるのです。
その意味で本件裁判例は、遺言書の内容にとらわれずに合理的な結論を導いた事例と評価できます。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所